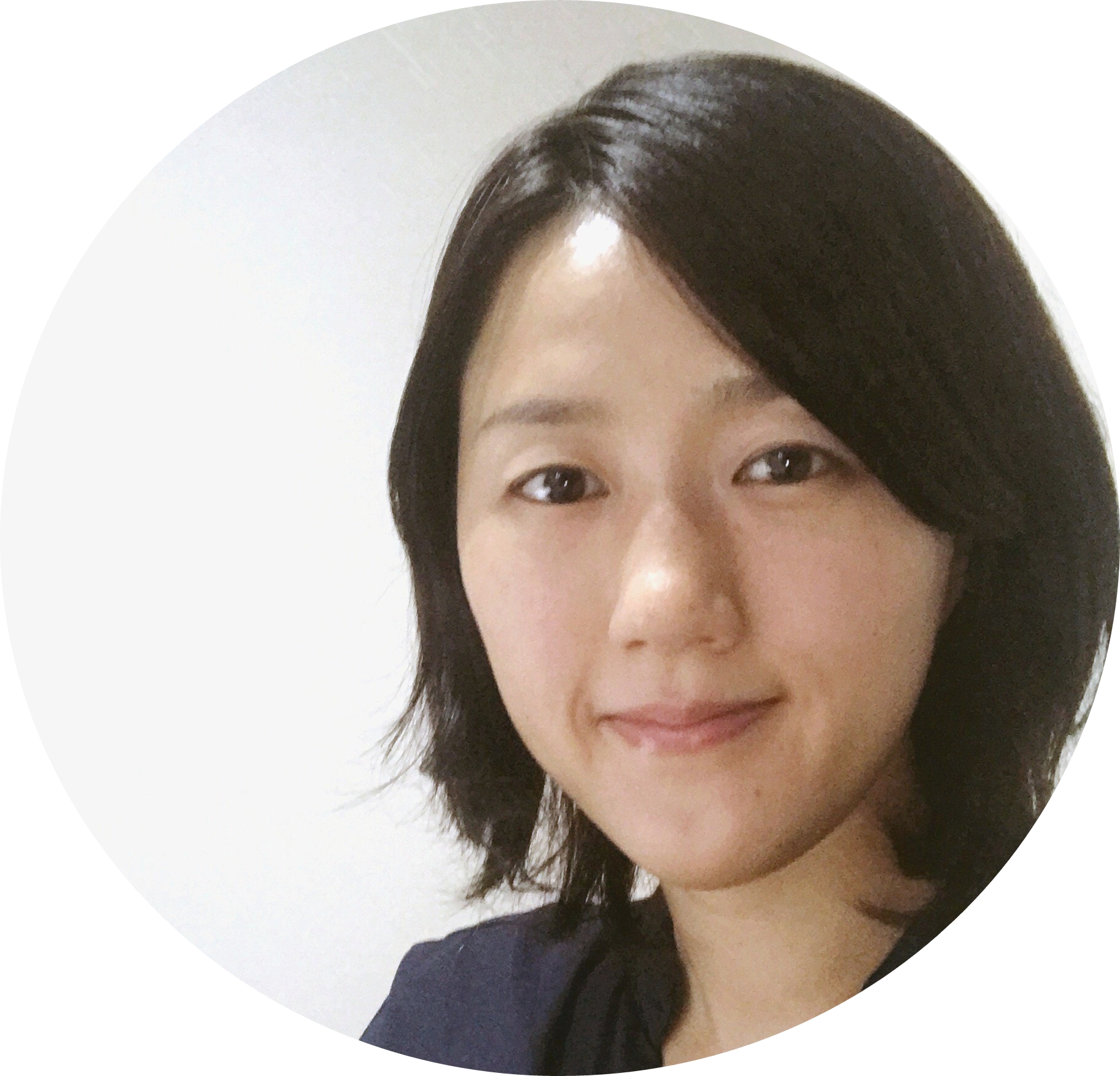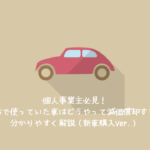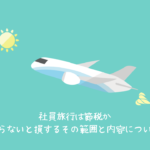近くにライバル店が出店したとき、あなたはどのような行動をしますか。
ある行動が、店の経営をもっと悪化させてしまうのです。
今回はそのある行動をした事例を、表を使って分かりやすく説明していきます。
目次
はじめに
ライバル店が近くに出店し、客足が徐々に遠のくこともあるかと思います。
その時、経営者であるあなたはどんな行動をとりますか?
「ある行動」をとると店の経営状態が一気に悪化し、存続の危機に陥るかもしれません。
存続の危機に陥る「ある行動」とは
先に答えを言ってしまいましょう。
答えは「値引き」です。
なぜ、と思われた方も多いかと思います。
値引きなんてよくある話ですよね。
お客様を呼び戻したくて値引きをする経営者の方も多いと思います。
しかし、その値引きは本当にお店のためになるものでしょうか。
値引きのメカニズムを知って値引きをするのと、
値引きのメカニズムを知らないで値引きを実行するのは、雲泥の差があるのです。
値引きのメカニズムを知らないで実行すると、お店をたたまないといけない状況まで陥るかもしれません。
事例|赤字に転落するまで
ライバル店が出店する前|お店の経営状況は
いつものごとく、会計の全体が見えやすい四畳半の図で説明します。
おしゃれなカフェ(飲食店)を想定しています。
出店してから、徐々に周りの人たちにも口コミで広まり人気が出てきました。
一日に40人の利用、25日営業で1,000人の計算です。
一人当たりの客単価とお店を利用してくれる人数、そしてお店全体の図は下記のようになっています。
利益も着実に出ている状況です。
ライバル店が出店|お店の経営状況は
経営も順調にいっていたある日、近くにライバル店が出店しました。
ライバル店の出店記念サービスもあり、当然客足はそちらに流れます。
そうすると、自分のお店では、お客の人数分経営にも影響してきます。
トータルで見ると売上の金額は100万円から80万円に減っています。
何が原因で売上が減ったか分かりますか。
お客の人数が減ったからです。
利益はかろうじて8万円出ています。
しかし焦った経営者は、客足を取り戻そうとあの行動をしてしまったのです。
ライバル店が出店後|経営者が行った策とは
はい、もう読んできた皆様ならお分かりですね。
値引きです。
お客様に戻ってきてもらおう、そして新規も獲得しようとの狙いから、なんと全品2割引きを決行してしまいました。
その結果、客足はライバル店が出店する前の1,000人に戻りました。
図では、客の単価1,000円だったのが、2割引きの800円になります。
最近はクーポンなど手軽に利用できるようになったので、2割引きくらいではインパクトに欠けるかもしれませんが、経営には大きなインパクトを与えます!
下記の図のようになります。
客の単価のV(原価)を見てください。
会計の頭になってるとここが落とし穴になります。
売上が減ったら原価も下がるはず?
原価率をかけて仕入れを計算するのでは?
さぁ、そこで質問です。
「お客様に値引きをしたら仕入れる値段が変わりますか」
もちろん、現場の経営者の方ならご存じのはず。
そう、売上をあげるために客単価を下げても、仕入れる値段は変わらないのです。
ライバル店が出店後|対策後の経営状態は
一時的に、客足は戻ってきましたが、私も含め客とは慣れる生き物です。
2割引きがいつでもやっていると分かればまた引いて行くのが常です。
さあ、経営状態はもう想像つきますね。
恐れていた事が起きました。
負のスパイラルです。
客単価で値引きをして客足が戻っても、赤字
このまま行っても赤字
さあ、次はどんな手を打ちますか。
ライバル店が出店したら|大事なポイント
経営で大事になってくるのは、客単価の粗利(M)と客の人数(Q)です。
いわゆる、粗利となってきます。
売上の金額でも仕入れの金額でもないのです。
粗利を確保するために、売上の金額や仕入れの金額があるのです。
値引きは「利益と直結」しています。
これが値引きが怖いメカニズムです。
事例から見ると、ライバル店が出店した後、お客さんが2割減った800人でもなんとか利益を出せていました。
しかし焦った経営者がとった策は値引きでした。
「値引きで2割減るのも、お客が2割減るのも同じ」と思ったのかもしれません。
方向性を誤らないためにも、客単価と人数を普段から意識して経営を行うことが大事になってきます。
さいごに
値引きのメカニズム、「利益と直結」していることが分かっていただけたと思います。
先程の事例では最後はマイナスとなりました。
方向性を間違わないためにもしっかりと見極めることが大事です。
参考図書
利益が見える戦略MQ会計
経営者にお勧めの、そして必読の1冊だと思います。(もちろん会計人にも)
参考までに
私の事務所のPRなので控えめに・・・
このマイナスを0にし立て直すためには、客の人数はどのくらい必要になるのか、なども数値として算出できます。
このことが理解できていると、漠然としてものではなく、様々な角度から具体的な方向性を見つけることが出来るのです。
私の事務所では、上記の表も使い月ごとの分析をしています。
次にどこに手を打てばいいのかなど数値から見える方向性も示しています。
色々な方向性を提案しつつも、最後に決めるのは経営者自身です!
少しでも自信をもってすすめるようお手伝いをしています。
本を読んでみて、内容は分かったけど具体的に数値をあてはめるのが難しいと感じられるかもしれません。
弊事務所では、お試しで価格で利用できるサービスも提供しておりますので、是非気になられた方はどうぞ。
https://omori-tax.site/getujibunseki-otameshi