商品などの在庫、沢山かかえていませんか。
その在庫にも税金がかかっているのを知っていますか。
今回は、棚卸資産や在庫について節税となる取り扱いを説明していきます。
目次
はじめに
小売業や飲食店などは、年度末などに「棚卸(たなおろし)」をします。
棚卸とは、実際に倉庫やお店などにどのくらいの商品があるのか在庫数を数え集計する作業のことです。
その集計作業の際、計算方法がいくつか定められており、その計算方法によって節税効果が期待できます。
また不良在庫など抱えている場合に、処分などすることで利益を圧縮する効果があります。
在庫商品と利益の関係
ここでは、そもそもなぜ在庫商品、棚卸資産に税金がかかるのか、どのように利益と関係があるのかを見ていきましょう。
商品の在庫は、「売上原価」と密接に関係しています。
事業をしていらっしゃる方は「売上」や「粗利益」などの言葉を聞くとピンくるでしょう。
売上原価は売上から粗利益をひいたもの、裏を返すと売上から売上原価を引くと粗利益となるのです。
言葉で説明してもいまいちなので、図をみてみるとすぐに理解できると思います。
期末の在庫の評価金額によって、売上原価が決まります。
売上-売上原価=粗利益
粗利益-固定費=利益
因みに期末の在庫が40に増えた場合は、下記の図のようになります。
(ほかの金額はそのままです)
いかがですか。在庫が10増えると、利益も同額の10(20-10)増えました。
この利益20のところに税金がかかってくるのです。
在庫の増減が利益にダイレクトに影響しているのが図より分かると思います。
在庫の評価方法
これまでの説明で、在庫商品の金額で利益が変わってくることが分かった頂けたと思います。
次にその在庫商品の評価方法を見ていきましょう。
この評価方法によっても、在庫商品の金額が変わってきます。
主に2つの方法があり、法人税法上では選択して適用できることとなっています。
原価法
中小企業の実務では、ほぼこちらの原価法が使用されています。
その原価法の中にも6つの方法があります。
- 個別法
- 先入先出法
- 総平均法
- 移動平均法
- 最終仕入原価法
- 売価還元法
低価法
国際的には低価法がメインで、日本でも上場企業に対しては低価法が強制的に適用となっています。
内容は、期末の棚卸資産の種類ごとに取得した価格と期末の時価を比較して低い方の金額を選択し評価する方法です。
原価法に比べると、評価金額が低く見積もれるので有利な方法となりますが、「時価」を証明するのが難点となります。
どの方法が一番いいのか
業種によりけりですが、一般の中小企業には低価法がベストと言えるのですが「時価」を証明できない場合が多いです。
時価を証明することが難しい場合には、原価法の中から選ぶことになります。
実務上は、ほとんどの中小企業で原価法を採用しています。
評価方法を選択し、届け出をしていない場合
評価方法を所轄の税務署長に届け出ていない場合には、「最終仕入原価法」で評価することとなっています。
因みに余談ですが、数多くの商品を取り扱う百貨店などでは、売価還元法が使われています。
在庫を評価する際の注意点
評価方法により、在庫商品の金額を低く評価でき、節税効果となるわけですが、税務署もあまくはありません。
評価方法はその都度コロコロと変えられないようになっています。
具体的には、新しい方法で評価したい場合、その評価方法を採用しようとする事業年度が開始する前日までに、所轄の税務署長に届け出が必要となります。
また届け出期限までちゃんと提出したからといって、コロコロと変更している場合、新しい届出の方法が却下される場合もあるので要注意です。
すぐにできる節税対策として
1.在庫の評価方法
一般の中小企業では、専門家など入っていない場合、評価方法を選択して届け出をしているところは少ないと思います。
何も届出をしていない場合「最終仕入原価法」で評価することとなります。
この評価方法は、言葉の通りですが、事業年度の最後に仕入れた商品の仕入れ単価によって、在庫商品の金額を評価する方法となります。
現在の事業年度でできる節税対策としては、その最後に仕入れる商品単価を抑えることです。
最後に仕入れる商品単価を少しでも安くできれば、在庫の金額も低くなるからです。
2.在庫の減らし方
在庫は多ければ多いほど、倉庫スペースやそれを管理するための人件費などの費用がかかってきます。
すぐに出来る在庫の減らし方や利益の圧縮方法として下記があげられます。
・売る場合
決算セール
見切り品
・仕入れた時より著しく価値が下がっている場合
評価損を計上
・廃棄する場合
処分した費用と廃棄した商品の価格を費用化して計上
さいごに
いかがでしたか。在庫にも税金がかかっていたなんて知らなかった方も多いのではないでしょうか。
これを機に、商品を仕入れる際には在庫の事や、評価方法も視野に入れ仕入れを行ってくださいね。
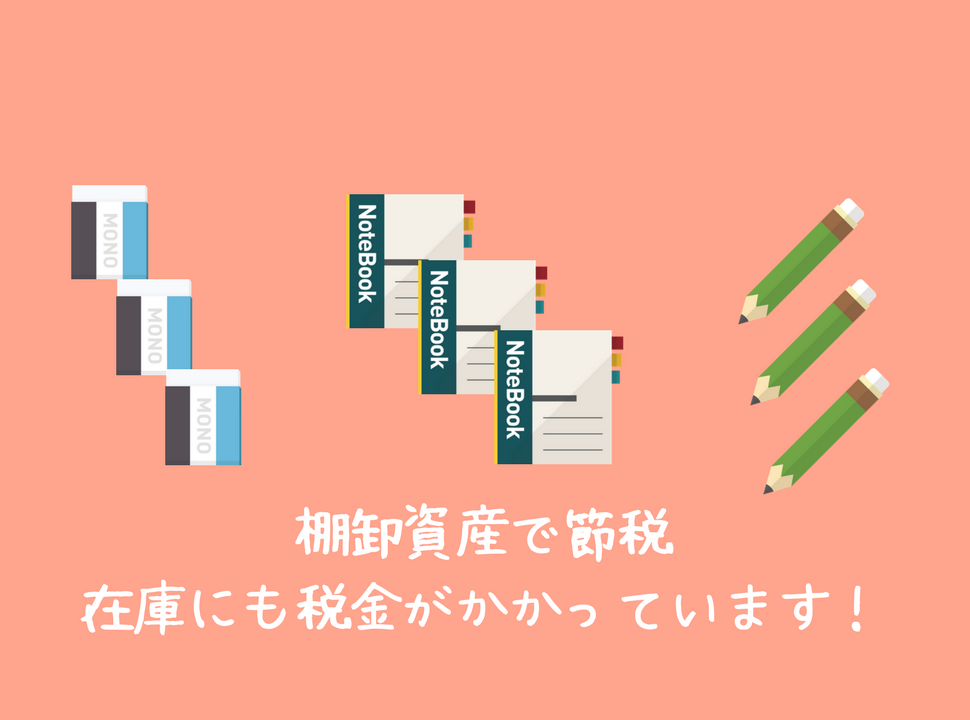


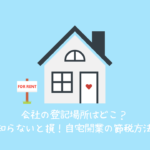
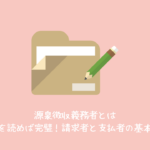

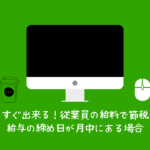

売上を変えずに在庫を減らすと節税になる。ということでしょうか?
捨てれば良いと?
読んでいただきありがとうございます。
その通りです。
売上が変わらなくても、在庫を減らすと節税になります。
不良在庫でしたら捨てるのも節税対策としての1つの選択肢となります。
数字上ではおっしゃる通りと思いますが、金額に直すと数字に矛盾が生じませんか。同じ商品で売上金額100万円で同じ場合、在庫数量・仕入れ数量を同じとしたら原価率も同じはずでは?
それとも、別の商品を、同じ商品として、比べているのでしょうか。
違和感があるので、コメントします。うまく伝えることができたでしょうか。
読んでいただき、またコメントありがとうございます!
返信が遅くなりすみません。
おっしゃりたいこと、伝わりました。
図ですと原価率が変わってくるようにみえますね。
しかし図の説明は、在庫が増えると利益が増えるロジックを説明しております。
会計でいう売上原価と原価率については分けてお考え下さい。
というのも、原価率は、例えば洋服を販売しているお店をイメージしてみてください。
赤のTシャツのみ、同じ業者から仕入れて販売するお店だとします。
10枚仕入れたとします。
一枚、売る値段1,000円、仕入れた金額700円
ここでいう原価率は、何枚買おうが原価率は70%です。
これが原価率です。
次は会計上どのように表示されるかです。
もしこの仕入れた赤いTシャツですが、すべて売れずに在庫でそのまま持っているとします。
会計上、仕入れ7,000円(700*10枚)、在庫7,000円(700*10枚)、売上原価0円となります。
このことからも「原価率」と「売上原価」はイコールではないことが分かって頂けると思います。
また何かありましたら、いつでもコメントください。
前期の在庫と期末の在庫の関係を教えてください。
前期の在庫より期末の在庫が少ない分、利益は少なくなるということですか?製造業なのですが、製品、仕掛品、原材料で仕分けして棚卸ししておりますが、すべて同じ在庫として考えていいのですか?
コメントありがとうございます!
その通りです。
極端な例を挙げてみます。
【 期首在庫 100 > 期末在庫 40】
売上が200万、前期在庫が100万、当期の仕入れが0円、期末在庫40万、だとします。
そうすると、売上原価は60万となり、売上 - 売上原価 = 粗利 (200 - 60 = 140) となります。
上記と同じ条件で、期末在庫のみを変えます。
【 期首在庫 100 > 期末在庫 60 】
期末60万だとすると、売上原価は 100 - 60 = 40
売上 - 売上原価 = 粗利 (200 - 40 = 160 ) となります。
当期いくら仕入れるかにもよりますので、前期在庫との関係というよりかは、期末在庫について少ない方が利益がかからないということになります。
在庫にも利益がかかるという観点からは同じ在庫として考えてOKです。
はじめまして 個人事業主のもとで経理事務をしているものです。天然石のアクセサリーを販売しています。ロットで購入する為在庫がふえていきます。家事消費として必要のない在庫を圧縮させると大幅に数値が落ちます。この方法を過去の申告にも修正申告として出すことは可能なのでしょうか?
はじめまして。コメントありがとうございます。
家事消費として必要のない在庫を使われると、「自家消費(家事消費)」として、売上科目に計上します。
ちなみに、この時には通常の販売価格の70%と仕入価格のいずれか高い方を、「自家消費(家事消費)」として計上します。
過去の申告に適用してもいいですが、売り上げも上げないといけないので、ほとんど効果はないです。
あくまでも当期の話です。
当期利益がでていて、前期からもっている売れない在庫を持っている場合、早く売るなり、処分した方が利益を圧縮できるといった話となります。
はげみになるので、またいつでも聞いてくださいね!